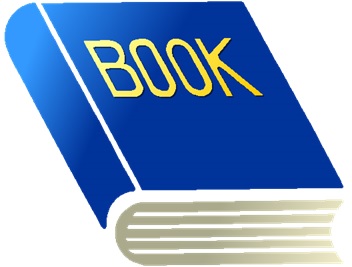

パソコンの部屋 趣味の部屋
「2025年に読んだ本」「心に残った言葉」「学習会の感想」
|
主催: 岡崎ホスピスケアを考える会 2月学習会 テーマ:終末期の意思表示 会場:岡崎医療センター2階 講師: 藤田医科大学岡崎医療センター 脳神経内科 伊藤信二先生 |
先生が示されたテーマは「嚥下・呼吸・循環をめぐる終末期の考え方」となっていた。 副題が「神経疾患において」 ・スライドは№51まであった。 ①スライド2=今回のテーマ → 1.終末期とは 2.神経疾患における終末期 3.家族にとっての終末期 ②スライド4=終末期の定義~九州大学病院ガイドラインから 1)~4)の定義があったが 「この定義に基づけば、今回の講演の目的は「終末期そのものの迎え方」ではなく「終末期に近づく状況下で、なおその人らしく生きるために可能な手段は何か」を考えることにある。(私たちの会の目的を理解してもらっている) ③スライド5-6=終末期は疾患によってさまざま さまざまな終末期 ・緩やかか、突然か ・えらくて動けないか、手足が動かないか ・頭はしっかりしている、認知症がある ・数日~数ヶ月、数年~十数年 (このような違いは、自己決定の可否に大きく影響する) 神経疾患では、できなくなることと、その時期を考えることが重要でできなくなる前に意志を聞いておくこと。 ④スライド9=終末期について考えなければいけないこと (どうしたいの意思表示) 生命維持→呼吸・循環・栄養の確保 意思表示→コミュニケーション手段 ↓ 家族・親族への継承(財産・権利など) 社会的継承(仕事・事業・役割など) これらを考えることは認知機能に左右される。いつまでに決め手おくべきか。 ⑤スライド10=重症脳卒中の終末期 → 自己決定の余裕はほぼない 数時間か数日で呼吸も心臓も止まるかもしれに状況下では、いちかばちかの治療をその場で家族が決めねばならない。 本人の意思表示は不可。 「命処置」や救命子得た場合の生命予後は通常数ヶ月~数年。 ⑥スライド12=ALSの終末期=全ての場合に選択・自己決定が必要で後戻りはできない 「日本では法的に中断はできない」 ⑦スライド18=終末期が訪れる時期はさまざま ・重症脳卒中:突然 ・ALS:半年~3年 ・パーキンソン:10年~20年 ⑧スライド30=胃瘻造設についての私見 ⑨スライド46=家族にとっての終末期 リビングウィルをいつ、誰が聞いた??(聞く?) ケア疲れなく、穏やかに後悔なく送るには ⑩スライド47=終末期の準備は遅れがち 疾患にかかわらず、元気なうちにどれだけ話し合っていたかに依存 ⑪スライド51=本人と家族に向けたスローガン 必要なのは特に若い人手だが、ヤングケアラー、ビジネスケアラーを作ってはいけない。 第三者の確保が必要。最悪なのは介護者が倒れること。 今回の学習会で再認識したのは 心身共に(突然倒れる前・認知症になる前)元気な時に話し合っておくこと。 実際私と同い年の人が昨年末にトイレで倒れてそのまま会話ができない状態が続いている。 3月末には、この新生「私のたまて箱」が完成する。これは最大のチャンスだ。 「終末期」というのは漠然と「老いて迎えが来る直前」のような気がしていたが、今回の学習会で若くても突然訪れることもある、その時のために、家族に自分の意思を伝えておく準備が必要だと痛感した。 |
| 2025年1月3日(金) 中日新聞 社説 「愛・地球博」にまいた種 2005年夫が亡くなった年です。 後がない状況の中で「愛・地球博」が開催されていることを知っていても、とても出かけることが出来ませんでした。勘のいい夫に気づかれないように、夫の兄弟には「地球博に来たついでに寄った」と言い訳を考え、5月末に予定していた見舞いには間に合いませんでした。 1月3日、この記事を見たとき、こんな大きな課題を掲げた万博だったことを初めて知りました。 ほぼ記憶から薄らいでいた夫の最期を鮮明に思い出させたこの記事。義兄からはこっぴどく叱られました。「何故もっと早く知らせてくれなかったのか」と。兄弟に会うこともなく逝ってしまったことに改めて悔いを思い出しています。 夫亡き後、義妹に連れて入ってもらい話の種に会場を見て回りました。 |
守るべき自然や四季を守りつつ、持続可能な社会につながる変革の種をまく-。愛・地球博のテーマを表しているのではないかと理解した。 メインテーマは「自然の叡智」。 再生可能エネルギー。太陽光パネルや場内から出た生ゴミをメタンガス発酵させてつくった電気を蓄電池にためて安定的に供給し、長久手会場の消費電力の1割を賄うことができた。 来場者のごみは9種類、出展者には17種類に分別してもらい、85%がリサイクルされた。いずれも今に繋がる課題解決のヒント。中でも想定外の人気を集めたのが「EXPエコマネー」 レジ袋を辞退すればポイントがもらえ、エコバッグや健康食品などに交換できる。 エコマネーセンターの来場者は延べ約60万人、発行ポイントは327万ポイントに上り、うち3分の2がレジ袋削減など場外での活動によるもの。 このように問題解決には「市民参加」が欠かせない。 長久手会場の「地球市民村」には、地球規模のさまざまな課題に取り組む国内外のNGO、NPO計約100団体が、月替わりでブースを出展。両者の本格的な参画は万博史上初めてのことだった。 <今日の社会を、明日へ。その次の世代へ。持続可能な社会、新しくなりながら続く社会のために。私にできることは、なんだろう。> あれから20年。再エネの普及は進まず、地球沸騰化に歯止めがかかりません。今や1年間で4万種の生き物が地球上から姿を消しています。海にはプラスチックごみがあふれ、早晩、魚の重量を追い越すことになりそうです。 まるで迷宮に入り込んでしまったかのように、愛・地球博が挑んだ課題の多くは未解決。しかし、だからこそ、愛・地球博という畑にまかれた小さな種は、地域に深く根付いていると信じて、今できる何かを探したい。そう願う年のはじめです。 一部抜粋 2025年1月5日記 |