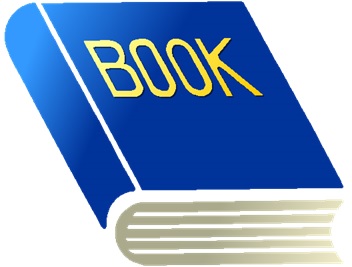

パソコンの部屋 趣味の部屋
2024年に読んだ本の記録
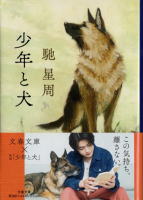 9月20日 馳 星周著 文芸文庫 |
久しぶりに目の離せない本を手にした。 震災後、仙台のコンビニの前にいた犬を手にした男。そこから犬の旅が始まる。名前は多聞。いつも南を気にしている。西に行くに従い西の方角をじっと見ている。次々と行き交う人を変えながら最後は九州まで辿り着く。「少年の犬」熊本でやっと探し求めた少年に会える。そこで初めて二人の関係が明かされる。旅の途中で行き交った人の最期を見届けてくるのだが、熊本でも震災に遭い少年を助けて自分が最期を迎えてしまう。 謎解きを進め、真相が知りたいために最後まで一気に読んでしまった。 奇しくもこの時、テレビで犬の帰巣本能についての実験をやっていた。2km離れた知らない場所から初めて会った人を連れて自宅に戻れるか。時間制限は日没まで。2匹でやっていたが両方ともちゃんと帰れた。本では東北から九州までだから比較にならない距離だけど、少年に会いたいという帰巣本能は確実に実を結ぶ。結末は意外だったが目的を果たせた多聞はもしかしたら幸せだったかも知れない。 孫のクリスマスプレゼント用に購入した本だった。読み終わったら孫の感想も聞きたい。 |
 2024年10月23日 小川洋子著 文春文庫 |
デパートの屋上で飼われることになった子象のインディラ。役目を終えて下に降ろそうと思ったが大きくなりすぎて降ろすことができない。臨終までここで過ごし、ボイラー室の壁とフェンスに囲まれた一角に小さな立て札が立ててあった。唇の奇形を持って生まれた少年。彼はこの場所が気になって仕方がない。そして唇の奇形から人との接触を避けるが回送バスの中で過ごすマスターにチェスを教えられ、その才能を見出され、対局を見ないでテーブルの下に潜り込んでその行方を見ることができる。しかし、そのマスターは甘い物が大好きで、また作る物がとても美味しい。食べ過ぎて太りすぎ、亡くなった彼を入り口から出すことができず、バスの屋根を破ってクレーンでつり上げて外に出した。ボス亡き後少年のチェスの旅が始まる。 私はチェスのことは全く知らないが、それでも面白くて引き込まれて読んで行った。人の集中力はすごい力を発揮するものだ。 時々出しては再度読みたい本の一つとなった。 |
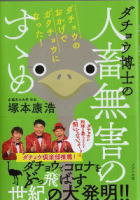 9月20日 塚本康浩著 ビジネス社 |
著者紹介から:1994年大阪府立大学農学部獣医学科卒業。1998年同大学院博士課程修了(獣医学博士)カナダ・ゲルフ大学獣医学部客員研究員。ダチョウ牧場「オーストリッチ神戸」のダチョウ主治医に就任し本格的なダチョウ及びダチョウ抗体の研究を始める。1998年大阪府立大学農学部・助手、2006年同准教授歴任後、2008年京都府立大学大学院生命環境化学研究科教授を歴任後、2018年~2020年同研究科長、2020年京都府立大学学長就任。 超大型鳥類であるダチョウを用いた新規有用抗体の低コスト・大量作成法の開発および、元細胞における細胞接着分子の機能解明とその臨床応用か、高病原性鳥インフルエンザ防御用素材の開発を研究。2008年京都府立大学発ベンチャー「オーストリッチファーマ株式会社」を設立。ダチョウの卵から抽出した抗体を用いて新型インフルエンザ予防のためのマスクを海発。以後もダチョウ抗体を利用した様々な研究(がん予防・美容など)に取り組む。 ダチョウ抗体マスク・ダチョウ抗体スプレー・ダチョウ抗体入り飴玉など次々とその国にあった品を開発し世界中で役に立つ物を作り出している。その開発のエネルギーに驚かされる。できるだけ現地で作る方が早いし新鮮ということで各国でダチョウを飼育することにも力を注ぐ。 最後に 「新型コロナのパンデミックで、ぼくは一八世紀の産業革命以降続いてきた社会構造や価値観が、変革の時期を迎えたのではないかと思うようになった。(中略) 歴史の大きなうねりに溺れてしまわないように、ぼくらも考え方を切り替えたほうがいいのかもしれない。「食う・寝る・交尾」しか頭になく、本能のままに生きて子孫を残してきたアホなダチョウに、サバイバルのヒントが隠されている可能性だってある。 次の目標は、ダチョウ抗体のがん検査薬を完成させること。ダチョウ抗体なら微量ながん細胞も見つけられ、安く大量に検査キットを作れる。 |
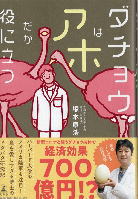 2024年9月17日 塚本康浩著 幻冬舎 |
数年前のコロナの頃にダチョウマスクでテレビによく出ていた。大学の構内をダチョウが自由に闊歩する姿が面白かったし、本気でダチョウを怖がっている姿もまた面白かった。(以前に遠慮ないキックで足を複雑骨折して松葉杖をついて画面に出ていた)とにかくとても面白い教授の印象だった。そしたら日曜日の新聞にこの教授の本が紹介されていたのでネットで2冊購入して読んだら面白くて止まらない。 2冊が同じような内容だったらつまらないと思っていたが、全然違っていた。やっぱり頭が良いのだなあ。初版が2021年3月と5月だったので3月の『ダチョウはアホだが役に立つ』から読み出した。コロナの頃に知ったので最近のことかと思ったら、ダチョウとの付き合いがすでに24年になるとのこと。アフリカのMERSやエボラ出血熱などにも予防できるようにダチョウ抗体を作り産学連携で人のために役立つ研究している。 「子ども時代は不登校でまわりからはアホやと思われた僕でも、大好きな取りにかかわりたいと思って生きてきた結果、感染症から人を守るという形で人の役に立てるようになった。ダチョウはアホやけど、その驚異的な生命力で僕ら人間の命を守ってくれ、ごっつ役に立ってくれている」 |
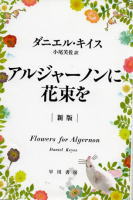 2024年7月19日 知能の低かったチャーリーが手術を受けることで高度な知能を勝ち取った。しかしその中で暮らすうちに何故か生きにくさを感じていく。その結果得たものが最後に表示されている。今自分たちの身の回りでとても大切なことを教えてもらった本だった。 最後はまた読みづらいカタカナや誤字脱字に戻っていく。手術はしたけれどやがてそれは消えていく。 「あとがき」がまた面白い。 ダニエル・キイス作品 長編: 『五番目のサリー』 (解離性同一障害の世界) 『24人のビリー・ミリガン』 自伝『アルジャーノン、チャーリー、そして私』 |
孫娘から借りた本。映画で観て内容は知っていたが本で読むのは初めて。ワクワクしながら読み始めたが、知能の低い時に書かれた最初の文章が誤字脱字が多く何とも読みにくい。なかなか進まないなか、やっとの軌道に乗ったら本当に面白い。中でも手術をし知能が上がっていくと本人の意思と関わりなく周りの人の理解が追いつかないことにいらだちや相手を見下す姿勢が出てきてしまい友人を失っていくあたり。 記憶に残った台詞などを書き留めておこう P9 チャーリーはこう示唆したいのだろう。つまり知識の探求にくわえて、われわれは家庭でも学校でも、共感する心というものを教えるべきだと。P9 P118 大学へ行き教育を受けることの重要な理由のひとつは、いままでずっと信じ込んでいたことが真実ではないことや、何事も外見だけではわからないということを学ぶためだということをぼくは理解した。 P243 手術前の彼は存在しないという教授の話。それに対して反論と反撃を感じるチャーリー。知能は上がっても決して術前の彼が存在しなかったことにはならない。 P290 チャーリーかねがね疑いを抱いていたのだが、あのチャーリーはやはり去ってはいなかったのである。人間の心の中にあるものは決して消えてしまわないのだ。手術は、彼を、教育と文化の化粧板でおおいはしたが、感情の面で、彼はまだそこにいて眺めながら待っていたのである。 P296 知識と知能 幼児はわが身を養う方法も、食べるべきものを知らなくとも、飢えは知っている。 私の知識と才能を、人間の知能の増進をはかる分野に寄与すべきである。これほどの能力をもった人間が他にいるか?両方の世界に住んできた人間が他にいるか? P300 おびただしい夢や記憶の渦にますます深く引き込まれるにつれて感情的な問題は知的問題のように解けるものではないことがよく分かっている。 で探し求めていたのは、人々とふたたび感情を分かち合える方法だった。 P363 「このまたとない機会がきみに与えたものはそれだけか。きみに与えられた知能は、世間に対する信頼、仲間に対する信頼を破壊してしまった」 チャーリー「それはまったくの真実とは言えませんね」と私は穏やかに言った。「知能だけではなんの意味もないことをぼくは学んだ。あんたがたの大学では、知能や教育や知識が、偉大な偶像になっている。でもぼくは知ったんです、あんたがたが見逃しているものを。人間的な愛情の裏打ちのない知能や教育なんてなんの値打ちもないってことをです」 P364 「誤解しないでくださいよ」「知能は人間に与えられた最高の資質のひとつですよ。しかし知識を求める心が、愛情を求める心を排除してしまうことがあまりにも多いんです。すなわち、愛情を与えたり受け入れたりする能力がなければ、知能というものは精神的道徳的な崩壊をもたらし、神経症ないしは精神病すらひきおこすものである。自己中心的な目的でそれ自体に吸収されて、それ事態に関与するだけの心、人間関係の排除へと向う心というものは、暴力と苦痛にしかならない。 |
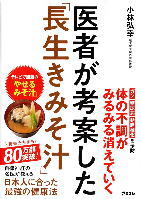 2024年4月21日 |
①「長生き味噌汁」が最強といえる理由 ・赤味噌=抗酸化力を高めるメラノイジンが豊富 ・白味噌=ストレス抑制効果のあるGABAが含まれる ・おろし玉葱=解毒効果抜群のアリシン、ケルセチンが豊富 ・リンゴ酢=塩分排出効果のあるカリウムが含まれる ②さらに病気を遠ざける 「長生き味噌汁」習慣のすすめ ・朝起きたら、コップ1杯の水をぐいっと飲み干す 飲んだ水の重さで、胃袋が大腸を刺激し、腸の運動が活性化する。 ・音楽とアロマの力でリラックス 音楽は自律神経のバランスを整える効果を発揮する。 アロマの香油には心身を落ち着かせる働きがる。 リラックス系=ラベンダー、カモミール、クラりセージ、など 就寝前にアロマを炊き、ゆっくりしたテンポのネイチャーサウンドの音楽を流す。 ・3行日記を書く 寝る前にひとりで机に向い、必ず手書きで、ゆっくりと、ていねいに文字を書く 副交感神経が高まり、質の高い睡眠がとれる。 ・4「長生きストレッチ」で腸の動きを改善する 腸の動きを改善するためのストレッチ。 朝起きたタイミングや、夜のリラックスタイムに、毎日5分間のストレッチを。 ・一汁一菜の「長生きみそ御膳」で自律神経を整える。 一汁一菜とは、主食 + 汁物 + おかず を1品ずつで構成した献立 食事の時間を「ゆっくりする、ホッと一息つく時間」にすれば、 できあがった栄養満点の食事との相乗効果で心も整っていく。 長生き味噌汁の作り方 材料=赤味噌80g 白味噌80g 玉葱150g リンゴ酢大匙1 ①玉葱をすりおろす(事前に冷蔵庫で冷やし、ゆっくりとすりおろす) ②①に赤味噌、白味噌、リンゴ酢を加え泡立て器で混ぜ合わせる。 ③10等分するように製氷皿にスプーンで分け、冷凍庫で凍らせる ④1個分を製氷皿から取り出し150mlのおゆを注ぐ ※具材を自由に追加するとなお良い。 |
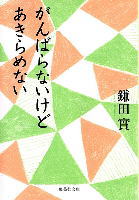 2024年4月12日 |
義妹に借りた本。他の用事もあり全く進まなかったけれど読み終われば大切な事が一杯書かれていた。 ・辛いときはとにかく笑いを探す。幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せになるのだ。間違いない。 ・アルフォンス・デーケン「死の哲学」=大変な数字を発表します。日本人の死亡率は100%です。「今73歳。自分の死も準備しなければなりません。お葬式は四谷の聖イグナチオ教会で行う予定です。お墓は同じ教会の納骨堂と決まっています。入る日は未定です。 ・健康な体をつくろう。運が必ずやっていくる。 頑張り続けていると常に交感神経が緊張状態になる。交感神経が緊張すると、リンパ球が減って免疫力が下がり、ガン抑制遺伝子にスイッチが入らない。頑張らないと時々思うことで体はホッとして力が抜け、副交感神経が刺激され、リンパ球が少し増え、免疫力が上がる。風邪を引いた時は頑張っていい。頑張ると交感神経が刺激されて顆粒球が増え、風邪や肺炎を克服しやすくなる。がんと感染症とでは病気を防御するシステムが違う。 「頑張らない」と「頑張る」のバランスが大切。 ・頑張らないけど諦めない 自分の生活を振り返ってみよう。美しい音楽を聴く時間がありますか。生き物や自然と触れ合う時間がありますか。大事な人たちとの繋がりを実感できる、いい時間がありますか。 もし答えがNOなら、今日から行動してみよう。そしてときどき自分ではない、ほかの人の心も、あったかくしてあげてください。 ・幸せの鍵はつながること 永さんの『あの世の妻へのラブレター』を読んでいると淋しいのは耐えられます。悲しいのも耐えられます。虚しいのは耐えられません。 ・自分らしく生きれば活路は開ける。きっと 悲しみのどん底にいるとき、悲しみだけを見つめないで、悲しみを横に置き、誰かのために生きることが大事なのかも知れない。誰でも自分が存在していることの意味が知りたい。自分が誰かの役に立っていると感じたとき、へこたれないぞと思えるのだ。 ・丁寧に生きればいい、人生はあなたを裏切らない。 |
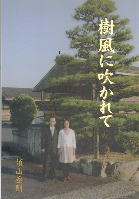 2023年12月入手 |
|
 2023年12月30日入手 |